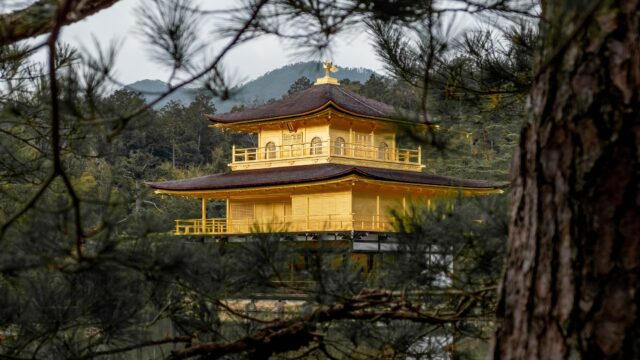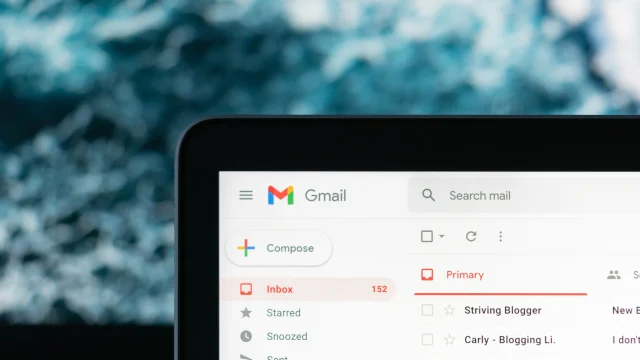建築現場において、設備(電気・衛生・空調・昇降機)という仕事は、あまり表舞台に出ない仕事です。それ故かつては虐げられる側面もありました。僕がこの業界に入った頃は「設備屋の仕事は夜やれ!」とか言ってる人が普通にいましたし、折角設置した配管を嫌がらせで外されたりしたいたエピソードさえも、、、人でなしかよ!って思いますよね。
また、現場監督によっては、設備のことには全く関心を持たず、全部丸投げにしているような人もいます。「あんなんは設備屋の仕事!俺は丸いものはしらんのや!!」って豪語していた先輩もいたなあ。。。
しかし、表題に書いたように、設備は「陰の主役」なのです。それがなければ建物は成り立たないし、上手く納めなければよい建物にはなりません。最近はBIMの普及で事前に設備納まりを把握することが容易になってきましたが、それでも技術者として、設備の図面を読み込み、建物内部に無理なく納める事が、現場技術者の重要な能力なんです。
1,建物高さの起点・排水設備
まずは排水設備。道路に埋設された下水道の埋設高さ(浄化槽を設置するところでは雨水管)と建物の距離が重要ですし、また屋内の配管についても天井裏・床下に適正勾配を設け、施工できるルートを確保する必要があります。
この基本中の基本、「必要勾配」と「施工できるルートの確保」が出来ていない設計図が多い。ざっくりと勾配と大きさを考えているだけで、実際の建物に合致していないのです。
それを設備屋さん任せにしていると、杭や基礎を打ってから「すみません、勾配が取れません」などという事になってしまいます。そうなれば本当に大変です。設備サブコンは、「設計図は正しい」という前提で仕事をしていますから、そういうことが起きてしますのです。
そうならない為に、「まずは建築屋が基本をチェックする」これです。
大体、排水のトラブルの種は決まっています。よく見かけるのは、
1,設計変更により位置が変わったのに、勾配・ルート検討をしてない
2,躯体貫通位置のルールを無視して勾配計算をしている
3,狭いPSに詰め込んで、施工性+構造検討を無視している。
4,他の配管設備(電気、空調ドレン、雨水、給水)の干渉無視
5,エルボ曲がりや配管の合流、通気ルートなどの検討が甘い。
他にもいろいろありますが、よく見るのはこれぐらいですか。
忙しい毎日ですから、これについてはどうしても手を抜きがちです。しかしひとたびこの類いのトラブルが起きると、何百倍もその対処に時間を取られてしまいます。であれば上記のようなトラブルになりそうな要素は建築の方である程度検討し注意喚起しておく、それが結局自分に時間が返ってくるのです。
サブコンさんは基本的には真面目な人が多いので、「課題を与えれば」誠実にその仕事をこなしてくれることが多いです。早く「気づかせてあげる」こと。全部を検討する必要はありません。ある程度慣れてくれば「お?ここは危なそうだぞ?」と思える場所が見えてくるようになります。
いかがでしょうか。設備図は建築屋にとって非常にとっつきにくいですが、慣れればその建物をよくするための、いろんなヒントが隠れています。最初から線を引くのではなく、楽しく理解することを心がけていけば、貴方の現場はとってもスムーズに運ぶ、良い現場になると思います。