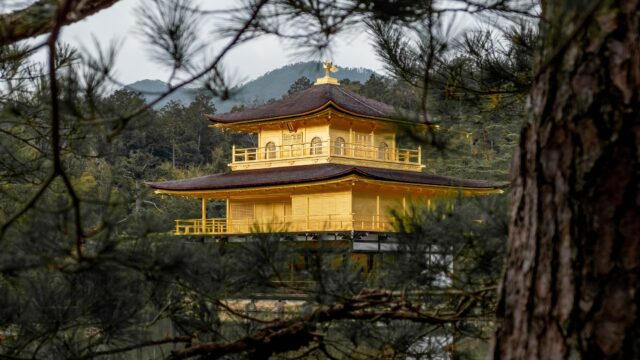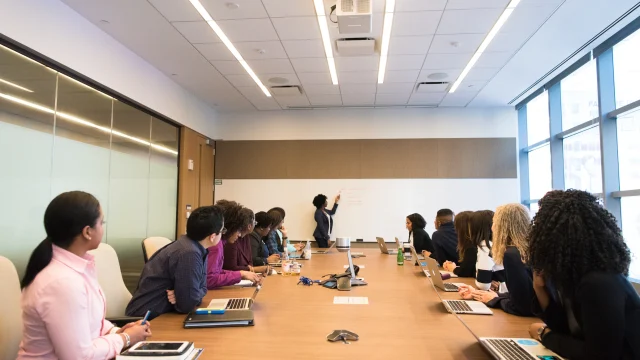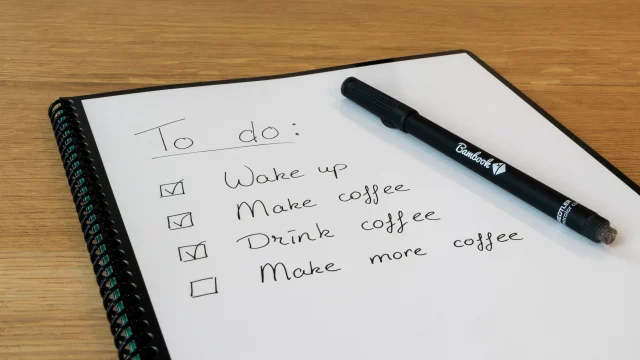約二年間、所長職を離れて、現場を指導する立場を続けてきました。正直、大変学びの多い二年間でした。特に若手所長のしなやかなチャレンジには拍手を送るばかりでした。
「しなやか」というのは自戒を込めています。
僕はどちらかというと上に反発し、正面から議論を挑んで押さえつけられることで、それを発憤材料に頑張る方でした。しかし今の若手所長は本当にクレバーというか、不要な争いをせず、ルールの中で上手く立ち回りながらやりたいことをするんですね。それは与えられたルールをとてもよく理解しており、その中でどこが改善点なのかを的確に見る「目」を持っているということです。
ドローン、点群測量、BIM、SNS、測量機器や検査システム、残業抑制施策に至るまで、そのアイテムの使い方の着眼点には感心することも多く、現場でその話を聞く度、ワクワクしていました。そしてそこで強く思ったのはこれでした。
今の面倒なルールを取払えば、もっとできるんじゃね?
そう、今現場を縛り付けているものを取り払うことで、より彼らに選択肢を与えることができるのではないか。そう思ったのです。
僕の所管するのは安全パトロールに関する事でしたので、この二年間でやってきたことを主に4項目、簡単に紹介します。同じ立場に立つ方が「現場のメンバーの改善活動を応援したいな」と思って、参考にしてくれるなら嬉しいなと思います。
1,巡回員への現場の説明は事前に済ませてしまおう
安全パトロールでいつも思うのは【前口上が長い】ということです。現場に着いてから現場員に「今現場はこういう状況です」と説明させ、それから現場に行く。これだけで約30分以上。しかも質疑の時間はほとんどない。これでは中身の濃い現場巡回は出来ないよ。って思いました。なので
現場に着く前に、現場情報は巡回員に詳細に説明しておく
ようにしました。幸いうちの会社はbuildeeで当日の作業内容と現場配置図を確認することができます。であれば予習しておけばいい。現場から事前に送って貰った使い回しの資料とともに、現場に行く人全員に前日、もしくは当日現場に着くまでに説明してしまうのです。
これで、現場に着いたら説明の時間を省いて、「あの、現在のこの工程やけど、ちょっと詰め過ぎてると思うけど」とか「今日の計画でのクレーンはこうなってるけど、吊り荷の下に入っちゃうんじゃないの?」などと、質問から始められるようになりました。その事前質疑を行った後現場に行けば、それぞれが問題意識を持って現場に行くことが出来るようになったのです。
2,資料を現場に用意させるのをやめよう
安全パトロールの準備って、現場にとって大変ですよね。配付資料の準備、会議室の準備、巡回員に対する案内、弁当の手配、現場によってはおしぼりや水分補給まで配慮してくれるところもあります。本当にやることが沢山で少ない人数の現場などでは、大きなストレスがかかります。なので、
紙配付資料は準備しなくて良い
ようにしました。事前にメールやフォルダで最新の工程表などの資料を共有してもらい、僕がそれを巡回員に事前に配っておく。前項の事前説明のときにどうせ必要になりますから、全く苦ではありません。それによって僕が深く現場の事を事前に知ることで、ポイントを絞った巡回が出来ます。現場にとっては配付資料・準備資料がなくなることはずいぶん楽になります。そして
パトロール専用のまとめ用紙の廃止
を行いました。今日の日付とか、無災害労働時間とか、現場のスローガンとか、主要作業とか「転記ばかり」の資料を書かせるのをやめました。そういうのはパトロール者が社内共有資料やbuildeeを確認すればわかることです。生産性のない書類はそもそも僕が嫌いです。現場が暇ならそれもよしですが、そういう現場はおそらくレア中のレアだと思いますので。
3,チェックリストは事前実施、現場目線に立ち減らそう
現場巡回チェックリスト。あなたの会社にもありますか?そして上手く機能していますか?
組織により様々ですが、僕が担当になった時そのチェックリストはもう膨大そのものでした。勿論、一つ一つは大切なことが書いてあるんです。でも全体を俯瞰して見た時に、疑問がふつふつとわいてきました(正確には現場所長の時から思っていました)例えば、
●これ、別に安全パトロールのチェックじゃなくても良くね?
●このリストと、このリストのこれ、同じこと言ってんじゃね?
●このルール、もう形骸化してるんじゃね?
●この項目、最初の会議で確認して終わってるんじゃね?
●こんな項目、わざわざチェックリストにまで挙げなくても良くね?
ってな具合です。で、削って削って削って。。。結果、チェック項目は、なんと、
・・・・・・・・・・半分になっちゃいました。
いや、本当そういうもんなんです。事故やトラブルが起こるとどうしても「ルールを上書き」するのではなく、足しちゃうんですね。だから無限にチェックリストが増殖する。で、後からそれを削るのは遠慮して出来ない。となってしまう。
勇気を持って「止めましょう」を言うこと。それは組織にとってハードルではありますが、超えられないハードルはありません。多くの人が今のルールに疑問を持って欲しいですね。
4,その場で修正できることは、指摘としてあげるのを止めよう
パトロールが終わった後、巡回員から何十項目の指摘事項が上がってきたら、そしてそこに「あの時、回った時にすぐに直したのに。。」と思ったことありませんか?そしてそれをわざわざ写真を撮りに行って、コメント書いて、アップロード。。。。
そういうの、止めました。
勿論、日常のルーチンの中で繰り返し起こりそうな要素があれば別ですが、単に隙間が空いてたとか、物を置き忘れているとかの軽微な物を指摘にしてしまうと、報告だけで現場は疲弊してしまいます。だから指摘事項は重点的なものだけを挙げ、複数の人から上がった同じ様な指摘事項は、一つの回答でできるよう、まとめるようにしました。
また、指摘の修正についても形を求める人がいます。写真の角度が悪いとか、よく見えないとか。。。酷すぎるのは修正させるべきですが、少々見づらい程度なら、あった時に口頭で言えばいいし、大事なのは「どう修正したか」ですしね。ただ、ちゃんとした現場担当者は指摘の修正写真もこだわりますので、言わなくても良い写真が出てくるんですけどね。
それぞれの立場で、やれることは、いくらでもある
いかがでしたでしょうか。本当はもっといっぱいやっているのですが、外に公表できるのはこのくらいなのですね。この二年のやり方の変化を現場側がどう思っているのかは、未来の人の課題ですので聞いてはいません。しかし一つだけ言えることは「現場と交わす議論の中身が深いものになった」ということです。
法違反を指摘するだけのパトロールなら、労働基準監督署に任せておけばいい。社内で行うパトロールは、現場に隠れた未来のリスクを現場の人とともに読み取り、それを指摘という形で具体的なやり方に昇華する。それが本当の安全パトロールだと思います。
また、言いっぱなしではなく「なんでこんなややこしいことになってるんですか?」「ここに困ってるので上手い解決法ないですか?」という疑問には丹念に根拠を調べて適切な回答を導き、具体化するのも巡回者の仕事です。それを怠って現場に投げ返す人のなんとも多い事か。そういう無責任だけはしたくなかったんですね。
僕の2年間は、そういう期間でした。それがどんな効果を生んだかについてはもう知るよしもありませんが、実績としてチェックリストを半分に減らしても、現場事故については減少したことを報告しておきます。勿論、決して僕の実績ではなく、現場メンバーの努力の結果。要は書類やエビデンスが減っても、気づかせてあげさえすれば、現場の安全は現場の努力で達成出来る。という証明がすこしできたのではないかなあ。そういう風に思っているところです。