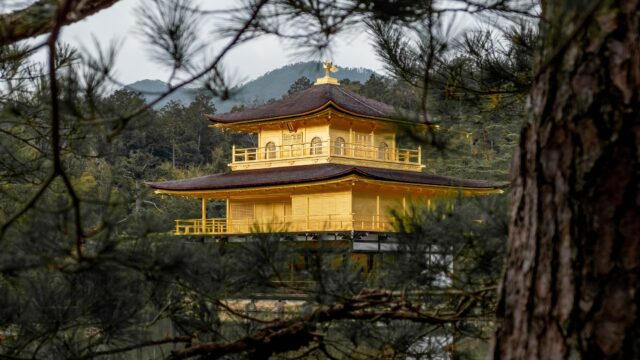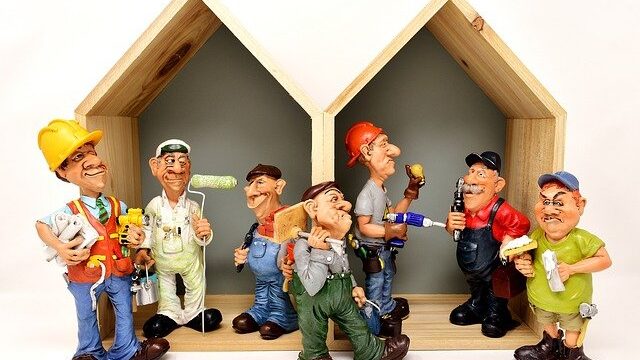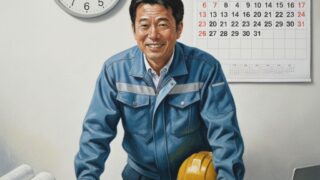8月末に、お世話になった会社を退職しました。
最終日にXにて、「現場監督を振り返って」という題でQCDSに分けて短文で回顧したのですが、ブログではもう少し詳しく書いてみたいと思います。
1,安全について思う
僕は、決して安全成績がいい現場監督ではありませんでした。無事故無災害を達成出来たのは予算数億の1現場のみです。ただ幸い僕が所長の現場では死亡災害はなく、それだけは本当に良かったと思っています。
では何故こんな成績が悪かったのか。第一は僕の注意力、計画力が足りなかったからですが、次の理由としては「馬鹿正直だった」(信頼する協力会社社長談)からかと思います。
作業員さんが埃が目に入ったとか、本人が「もう大丈夫」と言うちょっとした小さな怪我でも、蜂や毒蛾のような虫に刺されても医者に連れて行きました。またある時以降は、休業4日にこだわらず、安静が必要な怪我などは大事を取って休んで貰いました。
だから、支店の安全成績については申し訳ないが足を引張る方でした。しかし今となればそれで良かったと思っています。何故なら少なくない職長さんが「こうじや所長の現場なら来たい、次も呼んでくださいね」と言ってくれる理由が、「僕らの立場で物を考えてくれるから」と言ってくれたからです。確かに僕は理屈に合わないことが嫌いで、杓子定規な命令をできるだけ避けるようにしていました。締め付けが緩い分、それを勝手に解釈した人が事故を起こすこともありました。もう二律背反ですね。
でもその馬鹿正直さが職人さんに少しでも支持されていたのなら、まだ救いがあったかも?と思う所です。そして勿論職人さん思いの現場で、かつ安全成績がいい所長さんもいましたので、そういう方には心よりの拍手を贈るところです。決して安全成績が良くないことを正当化する意図はありません。僕らの無事故への挑戦は、いつまでも続くと思っています。
2,品質について思う
現場の品質管理は、悲喜こもごもというのが正直な感想です。
まず、僕は形式的な事が大嫌いです。特に若い頃ISOの洗礼を受けた身です。最初の頃は品質要求事項を満たすためにひたすら内容の重複した書類ばかりを作らされることに兎に角反発していました。ただでさえ忙しい現場管理、やるべき事も、学ぶことも満載な毎日の中で残してもその時以降誰も見ない書類と夜な夜な格闘する毎日。本当に嫌でした。
しかし、ただでは起きない僕です。どうせやるなら必要最小限にしよう。そのためには
少なくとも、審査する人よりもISOに詳しくなろう
これを目指しました。何かと言えば記録や文書にさせようとする流れを制止し、「要求事項には書いてないですよね!」って反論して新たなものを作るのを制する。とか考えていました。後にそれが凄く役立つ事となりました。できるだけコンパクトに書類をまとめられるようになったのはこの頃の経験のお陰です。
あと品質と言えば、人のトラブル対応に当たることが多かったですね。時には議会でも説明し、時にはテレビ放送に映ったこともありました。それぞれの事件では真摯に説明し、なんとか多くの人に納得を頂いたのですが、沢山の事例を見て思うのは「問題を先延ばしにすることの弊害」です。少なくとも僕の当たった事例はすべてなんらかの「決断の先延ばし」が絡んだものでした。自分の責任を回避したい、判断するだけの能力が足りない、そもそも問題点が発見できない等の理由で、正しい決断が先延ばしにされる。これがトラブルを大きくするのです。結局、品質管理とは
1,現場に存在する問題点をいかに早く発見できるか
2,その問題の軽重を判断できる素養・知識があるか
3,与えられた問題に対して、的確、迅速に対応策を判断しているか
について、「準備を適正に行っている」ことにつきます。そのためには、信頼できる部下や協力会社と要点を捉えた管理をすること、それに加えてそれに必要な「時間」を適正に確保することです。所長としてその意識を常に持っていれば、品質事故の発生する確率は限りなくゼロに近づけていけます。
以上、安全と品質に関して、詳しく回顧してみました。本当は具体的なエピソードをもっとかきたかったのですが、それはもう少し経ってからにしたいと思います。